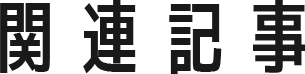株式会社いわきチョコレート
【福島県いわき市】会社全体を新たにブランディングし、
協業を強化した決断が再浮上のきっかけに
![]()
![]()
![]()
INDEX
企業情報
- 企業名 株式会社いわきチョコレート
- ヨミガナ カブシキガイシャイワキチョコレート
- 業種 食料品製造業
- 代表者 柳沼大介氏[代表取締役]
- 所在地 福島県いわき市小名浜字丹波沼61-1
- TEL 0246-53-5265
- WEB https://www.shiochoco.com/
- 創業年 2006年
- 資本金 1,500万円
- 従業員数 11人
- 売上高 8,231万円
企業概要
いわき市の魚メヒカリをかたどった生キャラメルをチョコレートでコーティングし、海塩を乗せた「めひかり塩チョコ」を開発。発売から90万箱を売り上げる。地元の酒蔵や果樹園とコラボした洋菓子の開発・販売も行っている。
フランス産塩チョコをヒントに名物「めひかり塩チョコ」を開発
福島県浜通り地方の最大都市であるいわき市。古くは炭鉱の町として栄え、近年は観光地としても多くの人々が訪れる町で、2006年に創業したのがいわきチョコレートだ。福島県内の老舗菓子店で20年近く商品開発を手がけてきた柳沼大介氏が、仲間や知り合いと立ち上げた。
「以前の会社を辞めた後、仲間たちとお菓子の新商品開発グループをつくって活動していました。そこで仲間の一人が、フランス旅行中にキャラメルが入った塩チョコを食べて衝撃を受けたと言う。似たような商品をすぐに購入して食べると、本当においしかった。それで商品化に向け動き出したのですが、なかなかうまくいきませんでした」。
グループのメンバーにはパティシエもいたが、キャラメルをチョコレートに閉じ込める工程に苦労したという。試行錯誤の末、固めたキャラメルにチョコレートをコーティングする方法なら、フランスの塩チョコに近い食感になることを発見する。その一方で、味のポイントとなる「塩」をどうするかが課題として残った。
「塩だけは福島のものを使いたいという思いがありました。『会津山塩』という有名な塩があったのですが、予算的な問題があり断念。いわき市に株式会社日本海水という製塩所があることが分かり、岩塩に近い粗塩を特別に作ってもらえることになりました」。
ちょうどその頃、いわき市の魚にメヒカリが認定され、市ではメヒカリに関連した加工品を募集。そこで、メヒカリの形に固めたキャラメルにチョコレートをコーティングして塩をかけるという「めひかり塩チョコ」が完成した。
 代表取締役の柳沼大介氏
代表取締役の柳沼大介氏




売り上げ激減で廃業も視野に入れる中、前を向かせた社員の言葉
会社設立の翌年、世間で生キャラメルブームが起き、「めひかり塩チョコ」も注目を集めたという。地元の観光スポットや道の駅などでの販売も始まり、認知度も徐々に上がっていく。しかし、2011年3月11日、東日本大震災に見舞われる。
工房の被害はほとんどなかったが、大口取引のあった観光施設の営業がストップしており、先行きがまったく見通せない状況に。柳沼氏は廃業も視野に入れた。被災してから約1カ月後に社員を集めて、店を畳む可能性もあることを伝えた。
「その時、社員の一人が『電気も水も通っていて、材料もある状態。甘いものを求めている人も多いと思うので、まずは店を開いてケーキなどを作って販売しませんか』と言ってくれたんです。その言葉で、悲観的にならずに今できることをやろうと、気持ちが切り替わったのは大きかったですね」。
翌日に店を再開すると口コミで広がり、近所の人だけでなくボランティアも来店し、にぎわいを見せたという。それでも、「先が見えない状況に変わりなかったので、不安な日々を過ごしていました」と柳沼氏は明かす。
復興庁の専門家派遣を活用し、ブランディングを再構築
店は継続しているものの、今後の展開が見えなかった柳沼氏の眼前に、一筋の光が差し込む。復興庁の専門家派遣集中支援事業だ。
「東日本大震災後初の商談会で知り合った『フルーツファームいとう』の方から、同ファームが栽培する『デュエット巨峰』を使ったチョコレート商品の開発を依頼されていましたが、なかなかうまくいかず、そんな折、復興庁の専門家派遣集中支援事業に採択されたんです」(柳沼氏)。
派遣された専門家から言われたことは、会社を新しい方向へブランディングし直すことだった。創業以来、「めひかり塩チョコ」はいわき市の土産品として知名度を上げ、売り上げを伸ばしてきたが、東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響もあり福島県全体の観光がどうなっていくか分からない状況。だからこそ、土産品から脱却して新しい方向性を示す必要があった。
「新しいブランディングをしているうちに会社がつぶれるのでは、という不安も正直ありました。しかし、地に落ちてしまった福島の食のブランド力を上げるためにも、世界一のおいしいものを作りましょうと言われ、自分たちのやりがいにもつながると、かじを切る覚悟ができました」。
デュエット巨峰で作ったレーズンを英海軍御用達のラム「パッサーズラム15年」に漬け込み、希少な白いカカオ「グランブランコ」を使ったフランス・ヴァローナ社の「イランカ」をガナッシュとコーティングに使用した「巨峰醇菓(じゅんか)」が2016年に誕生する。この商品が、いわきチョコレートの新しいブランドとして定着し、新たな動きにつながった。
商品開発への探究心が新たなブランディングにつながる
巨峰醇菓がきっかけとなり、福島県産のフルーツや酒を使ったコラボ商品が続々と誕生。情報発信にも力を入れ、積極的なブランディングを進めていった。2019年には、JR東日本の豪華寝台列車「TRAIN SUITE 四季島」に、めひかり塩チョコのプレミアムバーション「グランクリュ」が採用された。
「高級菓子を作らなかったら、この話はなかった。そういう意味でも新たなブランディングは間違っていなかったと思います」と柳沼氏は振り返る。その後も、「桃サンド&桃クッキーセット」「巨峰醇菓&紅玉醇菓セット」が採用され、いわきチョコレートの知名度を高めていく。
現在、売り上げは東日本大震災前を上回るまでに回復した。柳沼氏は、さらに県内でのつながりを広げていきたいと意欲を燃やす。
「今では、会社設立時に断念した会津山塩さんとも協業できています。新しいブランディングを始めた時は、ここまでの広がりは考えていなかった。どんなつながりがあるか分かりませんから、今後もさまざまなつながりを大事に、ブランド力を高めていきたいです」。
協業によって生まれる新たな福島の名産を全国へ届けるため、いわきチョコレートの先を見据えたブランディングを今後も強化していく。
 ショーケースに並ぶ「めひかり塩チョコ」。左端が「グランクリュ」
ショーケースに並ぶ「めひかり塩チョコ」。左端が「グランクリュ」
 小名浜の本店の看板。他に、いわき駅にも店舗がある
小名浜の本店の看板。他に、いわき駅にも店舗がある

・工房の被害はほぼなかったが、取引先の休業が相次いだため製造が完全にストップ。
・地元の観光業が先行き不安定な中、お土産を主体とした経営方針をどうすればいいか迷いがあった。

・地域の人々やボランティアのためにケーキなどの洋菓子を販売し、店が開いていることをアピール。
・復興庁の専門家派遣集中支援事業で新たなブランディングを提案され、高級志向の商品開発や独自の情報発信方法を構築。

・店が開いていることが口コミで広がり、多くの人が買い物に訪れ会社継続の足がかりとなった。
・新たに開発した商品がJR東日本の豪華寝台列車のメニューに採用。口コミで評判が広がり、売り上げも東日本大震災前を超えるまでに成長。