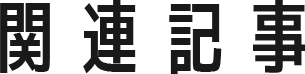株式会社おのざき
【福島県いわき市】「いわきの街の個性」である魚を通して
街をもっと面白くする100年企業
企業情報
- 企業名 株式会社おのざき
- ヨミガナ カブシキガイシャオノザキ
- 業種 飲食料品卸売業、飲食料品小売業
- 代表者 小野崎幸雄氏[代表取締役社長]
-
所在地
本社:福島県いわき市平鎌田町38
鮮場やっちゃば平店:福島県いわき市平字正内町80-1 - TEL 0246-23-4174(鮮場やっちゃば平店)
- WEB https://onozaki.net/
- 創業年 1923年
- 資本金 1,000万円
- 従業員数 100人
- 売上高 非公開
企業概要
1923年創業、1973年設立。1987年、株式会社おのざきに組織変更。福島県いわき市内に複数の店舗を構え、水産物の小売り、卸売りを行う他、飲食店を経営。2020年に4代目となる小野崎雄一氏が経営に参画し、経営改善を図って新事業にも取り組む。
被災2日後に店を開け行列。使命感に駆られて避難せず営業継続
「いわき市の街の個性を背負っている」。2023年に創業100年を迎えた株式会社おのざきのウェブサイトには、その自負と覚悟が記されている。幾多の苦境を乗り越え、その思いはますます強くなっている。
福島県いわき市内に複数の店舗を構え、全国でも名高い「常磐もの」をはじめとする水産物の小売り、卸売りを行うおのざき。東日本大震災では、小名浜の港に面した観光・物産センター「いわき・ら・ら・ミュウ」で営業していたすし店が津波で流されたが、それ以外の店舗の被害は軽微だった。
「鮮場やっちゃば平店」の店舗は、2日後には時間を短縮しつつも営業を再開した。「物流が止まって、周りのコンビニもスーパーも全部閉まっている状況。ここで生まれて育ててもらった地元の企業として、何としても店を開かなければいけないと思いました」と3代目で代表取締役社長の小野崎幸雄氏は振り返る。
水産加工品だけでなく飲料水も含め、在庫があるもの、中央市場で手に入るものを販売すると施設を取り囲む行列ができ、客からは「店を開けてくれてありがとう」という言葉をかけられた。「その言葉が胸に刺さって、使命感に駆られました」。東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響で避難する人が増え、周囲の明かりは消えていったが、「ここで暮らしているお客さまがいる限り、品物は提供し続ける」と自らは避難せずに営業を続けた。
2週間ほどたつと次第に状況は落ち着いてきたが、東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響で沿岸漁業、沖合漁業の操業が止まる。他の地域の魚介を中心に取り扱い、その後、試験操業が始まって地場の魚の取り扱いを再開したが、風評もあって売り上げが3割ほど落ち込む時期が続いた。
 代表取締役社長の小野崎幸雄氏
代表取締役社長の小野崎幸雄氏
地元事業者を支援するも経営危機に。4代目が経営改革で立て直しを図る
風評は売り上げ減少という直接的な被害だけでなく、事業者の心理的不安という二次被害も生み出してしまう。首都圏で復興支援の福島フェアが企画されても、心ない言葉を直接浴びせられるのではないかという心配から、参加する事業者は少なかった。
そこで小野崎氏は、つながりのある業者を集めて風評の払拭を目指すプロジェクト「ふくしま海援隊」を立ち上げる。「われわれは売るのが得意だから」と、地元の水産加工品を全国各地で売って歩いた。
そうした活動に奔走する一方で、店の経営は厳しさを増していた。おのざきが得意としてきたカツオやイカ、サンマといった大衆魚の水揚げが減少したことが大きな要因だ。経営管理に関わる社員も退職するなど危機的な状況に陥り、小野崎氏は長男の雄一氏に助けを求める。
雄一氏は大学卒業後、都内の大手スーパー勤務を経て、「いわきをもっと面白い街にしたい」と地元で飲食店を立ち上げる準備を進めていた。出店を断念することは苦渋の決断だったが、会社の状況を知って経営改革に乗り出す。ITも活用して経営状態の「見える化」を図って従業員に共有し、無駄を徹底的に省いて経費を切り詰めた。
「雄一が近代的な経営に変えてくれました」と小野崎氏。「私は昔から親父の背中を見てきて、出せば出すほど売れる時代でしたから、とにかく魚を売ればいいんだという考えでした。震災後はそんなことではやっていけない。スピード感を持っていろいろな決断をして、従業員も最初は戸惑ったと思いますが、次第に慣れていきました」。
その効果ははっきりと数字に現れる。「赤字続きでこのままいくと倒産だよなという状況から、会社を1、2年で立て直してくれました」と感謝する小野崎氏。「周囲には最初から雄一を社長にすると言って、みんな驚いていましたけども、今は誰も驚かないですよね。私はもっぱら現場で、雄一と従業員の間に入ってうまくやっています」と笑顔を見せる。




常磐ものの価値を改めて知り、時代に合わせ進化する「魚屋」に
雄一氏の経営参画後、鹿島の店舗を2020年に畳んだ一方で、2021年には平鎌田町にセントラルキッチンを新設。2023年にはいわき駅前の再開発ビルにある店舗、すし店をリニューアルオープンした。大衆魚の水揚げ減少、世帯構成の変化、嗜好(しこう)の多様化に対応し、仕入れた魚介を売るという旧来的な「魚屋」の商売スタイルから徐々に転換を図っている。
その一つが、洋風の総菜や未利用魚を活用した缶詰、レトルトの商品の開発。そこから誕生した「金曜日の煮凝(にこご)り」は、「ふくしまベストデザインコンペティション」キャッチコピー・ネーミング部門でGOLD賞を受賞した。
若者世代の食生活に合わせた商品開発、思わず手に取りたくなる洗練されたデザイン、ネットを活用したプロモーションなど成功要因はいくつかあるが、その根底にはやはり地元の魚のおいしさが一番にある。そのことを裏付けるエピソードを小野崎氏が明かす。
「例えば、毎年贈答品でヤナギカレイの干物を買っていたお客さまが、常磐ものがないので他の産地の干物を買って贈ったら『今までのとは違うんだね』と言われたそうなんです。私も震災後に他の地域の魚を食べて、常磐ものはもっと脂があるなとか、肉厚だなとか思っていたのですが、一般のお客さまからもそういう話を聞いて、われわれが売っていた魚は、やっぱりとてつもなくおいしい魚だったんだなと改めて気付かされました」。
一口食べて違いが分かるほどの水産物の宝庫が、目の前に広がる。それこそがいわきの「街の個性」であり、それをいかに発揮して次の時代につなげていくか。「こういう店に鮮魚を買いに来てくれるのは、やっぱり年配の方が多い。それを、若い人たちが来てくれるような楽しめる売り場にしていくことが、これからの課題だと思います」。
「魚を通じて街をもっと多彩に、もっと面白く」を掲げ、次の100年も続く企業を目指す雄一氏を小野崎氏は頼もしく見つめ、打ち出す次の一手を現場で支える。
 洗練されたパッケージデザインの「金曜日の煮凝り」も店頭に並ぶ
洗練されたパッケージデザインの「金曜日の煮凝り」も店頭に並ぶ
 鮮場やっちゃば平店に併設されている直営の食事処
鮮場やっちゃば平店に併設されている直営の食事処

・東京電力福島第一原子力発電所の事故による風評で売り上げが3割落ち込む。
・大衆魚の水揚げ減少、経営管理に関わる社員の退職で経営の危機に。
・世帯構成の変化、嗜好の多様化などによる魚食離れ。

・「ふくしま海援隊」を立ち上げ、地元の水産加工品を全国各地で販売。
・長男の協力により、コスト削減や経営の見える化など経営改革を図る。
・若者世代をターゲットにした商品開発や店舗展開。

・地元事業者の販路を広げ、自社の売り上げにもつなげる。
・赤字続きの状態から1、2年で脱却し、立て直しに成功。
・「金曜日の煮凝り」が「ふくしまベストデザインコンペティション」キャッチコピー・ネーミング部門GOLD賞受賞。