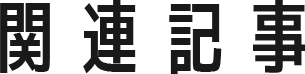合同会社MARBLiNG
【福島県飯舘村】個と個が折り重なりマーブル模様のように
緩く混ざり合う「最先端の田舎」を目指す
![]()
![]()
INDEX
企業情報
- 企業名 合同会社MARBLiNG
- ヨミガナ ゴウドウガイシャマーブリング
- 業種 その他のサービス業
- 代表者 松本奈々氏・矢野淳氏[共同代表]
- 所在地 福島県相馬郡飯舘村深谷字二本木前5-1
- TEL 0244-26-7720
- WEB https://www.zuttosoko.com/
- 創業年 2021年
- 資本金 53万円
- 従業員数 2人
- 売上高 非公開
企業概要
2021年、飯舘村の地域おこし協力隊の隊員だった松本奈々氏と、父親の影響で高校生の頃から飯舘村を訪れていた矢野淳氏が合同会社MARBLiNGを設立。翌年空き店舗を改修した「図図倉庫」をオープン。「最先端の田舎」づくりに取り組む。
就職のため上京するが新たな可能性に引かれて福島に戻る
福島県の阿武隈山系北部に位置する飯舘村は、山と川、田園が広がる自然豊かな農山村地帯で日本の原風景そのものだ。そんな魅力に満ちた飯舘村に感化され、この地を拠点に活動しているのが合同会社MARBLiNG(マーブリング)共同代表の松本奈々氏と矢野淳氏の2人だ。
松本氏は福島市出身。東日本大震災があった翌月に大学進学のため上京。卒業後はシステムエンジニアとして東京のIT企業に就職し、3年で退職。福島県相馬市で2週間のファームステイを経て、2019年4月に飯舘村の地域おこし協力隊の隊員となった。
 共同代表の松本奈々氏
共同代表の松本奈々氏
「隊員がやりたいことや興味があることを、飯舘村の資源をうまく活用しながら実現していくスタイルに魅力を感じた」と松本氏。「人がいなくなり、当たり前だった営みが止まったこの地で、何ができるかチャレンジしたら面白そうだという好奇心もありました」と続けた。
東京都出身の矢野氏は、父親がNPO法人を設立して飯舘村の復興に関わったのをきっかけに、高校生の頃から村を訪れるようになった。2020年に大学を卒業後、飯舘村と東京の2拠点で活動している。
分野や地域、世代の垣根を越えて多様な交流を実現する「図図倉庫」
飯舘村にとっても初めての地域おこし協力隊員の受け入れで、お互いに手探りの状態から始まったが、村の課題を共有しながら2人から活動を提案するようになったという。
当初はSNSでの情報発信が主だったが、村内の空き施設を活用してクリエーターの活動拠点や村内外の人々の交流拠点をつくるプロジェクト「Bound for IITATE」を企画。2020年3月に廃校となった村立小学校の2階にある大小さまざまな教室を、クリエーター向けの貸しアトリエやオフィス、コワーキングスペースなどに改装した。
 村内の祭りやイベントにも出店するキッチントレーラー
村内の祭りやイベントにも出店するキッチントレーラー
「クリエーティブ系の個人や企業が自然豊かな農村地域に集まることで、多拠点生活のモデルになればと。将来的には多様なジャンルの人たちが集まって、村民を含めた交流やコラボレーションが生まれる場にしたいと思って立案しました」と松本氏。
オンラインでプロジェクトに関わるクリエーターの募集を行ったところ30人ほどが参加。ユーチューバーや音楽家が飯舘村への移住を検討し、実際に移住したケースもある。
さらに隊員として満期を迎えようとしていた2020年の年末。村長の杉岡誠氏から「東日本大震災の影響で営業停止したホームセンターの建物を、使いたい人がいるなら解体せずに譲ってくれるそうだが、興味はないか」と直々に誘いを受ける。松本氏は「ありがたい話で即答でした」と当時を振り返る。
こうして新しい活動拠点を得た松本氏と矢野氏は、傷みが激しかった建物をボランティアスタッフと共におよそ1年半をかけて改修。2022年11月にシェアスペースをオープンした。
 ホームセンターを改装してオープンした
ホームセンターを改装してオープンした
「キーワードは村の地域環境づくり。村民も主役、外から来た人も主役となれる場を提供したい」と松本氏。名前は「ずっと」続くようにとの願いを込め「図図倉庫(ズットソーコ)」に。科学者による放射線の実験・研究、アーティストの制作活動、企業などのシェアオフィス、キッチントレーラー、村民と協働した商品開発など、多様な人たちが集い交流できる場となっている。まさに壮大な社会実験場といってもいい。
 放射線について学べる観測装置
放射線について学べる観測装置
得られたものは、支えてくれる仲間と伴走してくれる支援者の熱意
図図倉庫をはじめMARBLiNGの活動を支えているのは村民やボランティアだけではない。東京電力福島第一原子力発電所の事故の被害が福島県の中でも大きく、住民の帰還が遅れている浜通り13市町村の青年らが2021年に連携、設立した「HAMADOORI13(はまどおりサーティーン)」もその一つ。同団体の若手起業家応援事業「フェニックスプロジェクト」の第1期にMARBLiNGが採択された。
 「フェニックスプロジェクト」の認定証
「フェニックスプロジェクト」の認定証
年間上限1,000万円で3年間、東日本大震災復興支援財団の出資を受けられる同事業。松本氏は「資金に余裕が生まれたことで自分たちのやりたいことが進んでいきました」と話す。資金は図図倉庫の設計費や改修費、それに伴う人件費、商品開発費にも充てた。
プロジェクトの事務局は、資金援助だけでなく採択事業者が抱える課題の解決に一緒に取り組んでくれるという。松本氏は「採択事業者を交えた定例会があって、その場でお互いの課題や改善に向けたアドバイスもしてくれます。伴走してくれている安心感が生まれました」と頼もしい仲間に感謝している。
古いものが新しく見える 最先端の田舎でイメージを変える
 イベントで活用したビニールハウス
イベントで活用したビニールハウス
東日本大震災後、一時は誰も住めなくなった飯舘村でしっかりと一歩を踏み出したMARBLiNGだが、一体何を目指すのか。松本氏からは「MARBLiNGが目指すのは、単純に近代化、都市化するのではなく、先人たちの知恵や文化を生かした『未来の田舎』です」と返ってきた。
その思いはすでに形となって表れている。図図倉庫内のオフィス兼コワーキングスペースでは、稲を収穫し脱穀した後に大量に残るもみ殻を、袋に詰めて断熱材として活用。これは断熱材のなかった頃に編み出された防寒の知恵だ。さらにもみ殻は、地面に立てた煙突に入れ火を付けて炭にする「燻炭(くんたん)処理」を行う。その過程で発生した煙を冷やして精製すると、「もみ酢液」という土壌改良材の原料にもなる。しかしそのままではタールなどの有害な成分も含まれてしまう。そこで蒸留処理を行い、それらを取り除いたことで商品化に成功した。ホームセンターなどで売っているもみ殻やもみ酢液に比べて、MARBLiNGでは少量で販売しているため、ガーデニングや家庭菜園を行っている人たちから喜ばれたという。また、使用者からは、虫が付きにくくなったとのうれしい声もあった。
飯舘村で昔から当たり前に行われてきたことが、都会の人には新しいものに見える。こうした「最先端の田舎」を発信し田舎のイメージを変えていきながら、人と自然、都会と田舎の境界線を緩く消していく。それがMARBLiNGの目指すところなのかもしれない。

・図図倉庫の改修に伴う資材費や人件費など、費用の捻出に苦慮していた。
・米を脱穀した際に残る大量のもみ殻は、各農家がお金をかけて廃棄処分していた。

・若手起業家応援事業「フェニックスプロジェクト」の第1期補助事業で採択され、3年間の資金援助を得る。
・もみ殻を買い取り、建物に使用できる断熱材に再利用。さらに「燻炭処理」で発生した煙を冷やして精製する土壌改良材である「もみ酢液」を、家庭菜園や観葉植物用に改良し商品化した。

・資金援助を図図倉庫の改修費や商品開発研究に充てることができ、事業計画を進めることができた。採択者同士のつながりもできた。
・図図倉庫ブランドとしてもみ殻やもみ酢液を販売することでMARBLiNGの周知にもつながった。