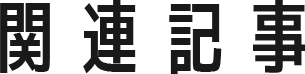有限会社谷地林業
【岩手県久慈市】新規事業や機械導入で生産性を向上
生産量が約4割増え、効率化を実現
![]()
![]()
![]()
INDEX
企業情報
- 企業名 有限会社谷地林業
- ヨミガナ ユウゲンガイシャヤチリンギョウ
- 業種 林業/総合工事業
- 代表者 谷地譲氏[代表取締役]
- 所在地 岩手県久慈市山形町荷軽部3-18
- TEL 0194-72-2221
- WEB https://www.yachiringyo.com/
- 創業年 1916年
- 資本金 2,000万円
- 従業員数 80人
- 売上高 非公開
企業概要
1916年に創業。創業から続く木炭製造の他、製紙用やバイオマス発電用の木質チップ製造、山林の伐採や育林を行う森林整備、土木工事をメインとする建設業を展開。木炭においては、年間約100tの生産量を誇る。
外部への販売事業と大型機械の導入で働き方を改善
古くから日本一の木炭生産量を誇り、「木炭王国」とも呼ばれる岩手県。広大な森林を有し、国内生産量のおよそ4割を占めている。1916年に創業した有限会社谷地林業は、100年以上にわたり、岩手県の製炭業を支えてきた。
岩手県ひいては日本の製炭業をけん引してきた谷地林業だが、昭和中期のエネルギー革命によって、主なエネルギー源が木炭から石油に移行し、木炭の生産量は年々減少。さらに平成以降は地方の人口減少に伴う働き手の不足や、高齢化の進行など、多くの課題を抱えていた。
そんな中で起こった2011年の東日本大震災。人口減少がますます加速し、地方産業の衰退も見込まれたが、代表取締役の谷地譲氏は「もともと頭の中で考えていたことを実行するきっかけとなったのが東日本大震災でした」と語る。ピンチはチャンスだと捉え、売り上げ拡大に向けてさまざまな施策に取り組み始めた。
 代表取締役の谷地譲氏
代表取締役の谷地譲氏
まず着手したのが、カラマツやアカマツなどの木々を丸太材として販売する新しい事業の展開だ。従来の木炭や木質チップの製造などの木材の加工だけでなく、材料の供給も行うことで、新規の顧客や取引先の獲得に成功。外部に向けた販売事業を始めたことで、社内で変化が生じたと谷地氏は振り返る。
「これまでは木炭や木質チップを流通業者に卸すだけだったので、社員は自分たちの仕事が会社にどれくらい貢献しているのかが分からない状況でした。外部への販売を始めたことで、数字が可視化されるようになって、目標も立てやすくなり、社員のモチベーションアップにもつながりました」。
それと同時に、長年の人手不足を解消すべく、岩手県や林野庁からの補助金などを活用して大型機械を導入。木の伐採から枝払い、丸太に切る「ハーベスタ」や、丸太を等間隔に切りそろえる「グラップルソー」、切りそろえた丸太を荷台に積み運搬する「フォワーダ」などを取り入れ、作業の省力化を図った。こうした大型機械の導入によって作業効率が大幅に改善され、生産量は約4割アップ。また、これまで人間の手で行われていた作業が半自動化されたことで、従業員の負荷が大きく軽減し、安全な労働環境の確保にもつながったという。
 大型機械「グラップルソー」導入により、木材の運搬や積み込み作業が効率化された
大型機械「グラップルソー」導入により、木材の運搬や積み込み作業が効率化された
「もちろん人の手が必要な部分もありますが、機械で代替できる部分はどんどん導入したいと思っています。最近では高齢化により現場を退くベテラン社員も増えてきましたが、効率化・省力化を図ることで、代わりに入った若い社員が安心安全に作業できるような環境づくりに努めていきたいです」。
適正価格で販売するため海外展開でお墨付きを獲得
創業より続く製炭事業においても、売り上げ拡大を目指した取り組みを行っている。岩手県産の木炭は、火付きの良さや火力の持続性、炭が爆発するように弾け飛ぶ「爆跳(ばくちょう)」の少なさなどが主な特長だ。また、不純物が少なく煙や臭いが発生しにくいことから、キャンプやバーベキューの愛好者をはじめ全国にファンが多い。一方、流通段階では品質の良さが伝わりきらず、安価で販売されてしまうという課題があった。
「木炭の値段は流通業者さんが決めるのですが、海外から輸入される安価な木炭と同等に扱われることで本来の適正価格で売ることができず、国産の木炭がもうからない状況が続いていました。そこで考えたのが海外展開です。木炭を海外に輸出し、海外で品質の良さにお墨付きをいただく。その評価を日本にフィードバックすれば、高値で売ってもらえるのではと思いました」。
 主力商品である「黒炭(KUROSUMI)」は、火力が強く長持ちする特長がある
主力商品である「黒炭(KUROSUMI)」は、火力が強く長持ちする特長がある
そこで谷地林業は、一般社団法人岩手県木炭協会と協力して2018年に「岩手木炭」を、地域の知的財産としての保護を目的とした「GI制度(地理的表示保護制度)」へ登録。それを契機に、海外への商品展開に着手した。2023年6月には、自社で製造した岩手木炭の輸出を、フランス向けにスタート。その品質は、海外でも高い評価を受けつつある。さらなる販路の拡大も視野に入れて自社ブランド「黒炭(KUROSUMI)」も展開を開始し、革新的な取り組みは今後も注目を集めていきそうだ。
事業自体がSDGsそのもの 100年先のより良い未来を目指して
谷地林業の事業では、木材が欠かせない。そのため木々を伐採した場所に苗木を植え、育てる「森林整備事業」に取り組み、持続可能な社会の実現に向け、50年、100年先も資源を利用できる循環型の林業を目指している。
「先人の方々が森林を育ててくれたからこそ、今、自然の資源を利用した事業ができています。次の世代につなぐためにも、われわれがアクションを起こさなければいけません」。
森林整備以外でも、持続可能性を意識した取り組みを実施している。木質チップ製造においては、新たにバイオマス発電用の燃料用チップを供給。東日本大震災以降、発電方法の見直しによる需要の拡大も相まって、売り上げは従来の約3倍を記録した。さらに木炭製造事業では、2023年より環境の改善に効果のある「バイオ炭」の生産を本格化。クリーンエネルギー社会の実現に向けた取り組みも行っている。
 製造している木質チップ
製造している木質チップ
 木材を加工する様子
木材を加工する様子
「世の中ではSDGsの重要性が叫ばれていますが、われわれの業界では昔から当たり前の話。弊社の事業自体がSDGsそのものであり、これまで通りの事業を続けていくことで、より良い未来につながっていくと考えています」。
 植林を行う様子
植林を行う様子
大正から令和まで、100年以上もの歴史を紡いできた谷地林業。この先の100年も豊かな自然を守り、資源を大切に利用しながら、さまざまな革新的な事業を通して、岩手の製炭業を先頭に立って引っ張っていくだろう。

・地方の人口減少に伴い働き手の不足、従業員の高齢化が進行。
・木炭などの流通業者へ卸すことがほとんどだったため、従業員は売り上げや会社への貢献度が分からなかった。

・東日本大震災後に大型機械を導入。手仕事だった作業を半自動化することで省力化を図った。
・カラマツやアカマツなどの木々を丸太材として販売。従来の自社製造に加えて材料供給型の新たな販路を開拓した。

・作業効率が飛躍的に向上したことにより生産量は約4割アップ。作業の半自動化で従業員の負担軽減につながった。
・外に向けた商売を行うことで売り上げの数値が可視化される。従業員のモチベーションアップにつながった。